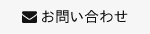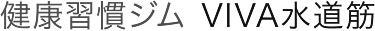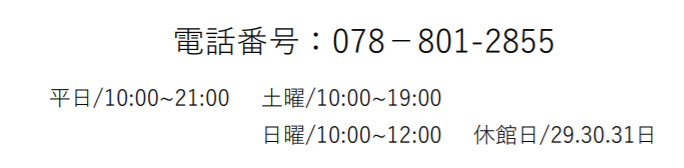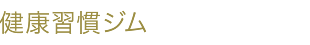ストレスは無くせない。だから「対処力」が大切
「ストレスを感じないようにしましょう」
よく聞く言葉ですが、正直それは現実的ではありません。
仕事、人間関係、環境の変化。
ストレスは日常生活に必ず存在します。
大切なのは ストレスをゼロにすることではなく、溜め込まないこと・抜けやすい状態を作ること です。
◆ ストレスが体に与える影響
ストレスを感じると、体は「交感神経優位(緊張状態)」になります。
この状態が長く続くと…
肩こり・腰痛が取れない
寝つきが悪い、眠りが浅い
疲労が抜けにくい
食欲の乱れ
といった不調として現れます。
つまりストレスは「心」だけでなく、体の機能低下として表面化します。
◆ ストレス対策の基本は「自律神経」
自律神経は
交感神経(活動・緊張)
副交感神経(休息・回復)
この切り替えがスムーズなほど、ストレスは溜まりにくくなります。
逆に、切り替えが下手になると、常に緊張状態から抜けられません。
◆ 今日からできる、現実的なストレス対策
1. 呼吸を整える(最優先)
浅く速い呼吸は、交感神経をさらに刺激します。
おすすめは
「吐く時間を長くする呼吸」
・4秒吸う
・6〜8秒吐く
これだけで副交感神経が働きやすくなります。
2. 入浴で強制リセット
シャワーだけで済ませている人ほど、ストレスが抜けにくい。
38〜40℃で10〜15分の入浴は、
副交感神経を優位にする“スイッチ”になります。
3. 睡眠を十分にとる
睡眠不足=ストレス耐性の低下。
寝不足の状態では、同じ出来事でも強いストレスとして感じやすくなります。
「まず寝る」
これは最も効果が高く、再現性のあるストレス対策です。
4. 栄養で神経を守る
ストレス下では、神経系の栄養消費が増えます。
特に重要なのは
マグネシウム(神経の興奮を抑える)
ビタミンB群(エネルギー代謝・神経機能)
糖質(脳のエネルギー源)
極端な糖質制限や欠食は、ストレス耐性を下げます。
ストレスに強い人とは、
「我慢強い人」ではなく「回復が早い人」
日常の小さな習慣が、
心と体の余裕を作ります。
是非、意識してみましょう(*^^*)
年末年始の疲れをリセットする``疲労回復術``
こんにちは、百です(*^^*)
年末年始は楽しいイベントが多い一方で、実は 一年で最も疲れが蓄積しやすい時期。
仕事の忙しさ、食生活の乱れ、睡眠リズムの崩れ——
気づけば「体が重い」「だるさが抜けない」という声がとても多くなります。
ここでは、年末年始に起こりやすい疲れの原因と、その疲れを確実に取るための栄養・生活のポイントをまとめます。
◆ なぜ年末年始は疲れるのか?
1. 食べすぎ・飲みすぎで内臓が疲れる
忘年会・おせち・お酒…
普段よりカロリーが増え、肝臓・胃腸がフル稼働。
内臓の疲れは、全身のだるさにつながります。
2. 睡眠リズムが崩れる
夜更かし、朝寝坊、昼寝の増加。
体内時計が乱れ、疲労回復に使うはずのホルモン分泌が低下します。
3. 運動量が激減
寒さ+休日で身体を動かす機会が少なくなると、
血流が悪くなり疲労物質が滞りやすくなります。
4. ストレスの蓄積
仕事の締め、家族行事、予定の詰め込み。
精神的な疲れは睡眠の質を落とし、結果的に疲労をため込む原因に。
◆ 年末年始の「疲労」を抜くための栄養ポイント
1. エネルギーを作る材料「糖質」
疲れを感じやすいのは、単純に“ガス欠”状態だから。
年末年始の乱れた食事では、必要なタイミングで糖質が入らず、逆にだるさが出ることがあります。
おすすめ:
・おかゆ
・雑穀ごはん
・バナナ
内臓に優しく、回復しやすい糖質です。
2. 肝臓にやさしい「ビタミンB群」
お酒・脂の多い食事で、肝臓は年末年始かなり疲れています。
ビタミンB群は、糖・脂質の代謝を助け、疲労物質を処理する働きをサポート。
食品例:
豚肉
納豆
卵
玄米
3. 鉄分で“酸素運搬力”を回復
鉄不足は隠れ疲労の代表。
年末年始は不規則な食事で鉄が不足しがちです。
おすすめ:
赤身肉
あさり
ほうれん草
レバー
(+ビタミンCで吸収UP)
4. マグネシウムで筋肉と神経を整える
暴飲暴食・運動不足の影響で筋肉がこわばりやすい時期。
マグネシウムは筋肉のリラックスに深く関わっています。
食品例:ナッツ、海藻、豆類、玄米
※マグネシウムサプリも超オススメ!
5. 抗酸化物質で“細胞のサビ”をリセット
ストレスや飲酒は、体内に酸化ストレス(サビ)を増やし、疲労を悪化させます。
おすすめ:ベリー系、緑黄色野菜
◆ 食事以外で必ず押さえたいポイント
1. 入浴で血流を回復
シャワーより湯船。
38〜40度で10〜15分がベスト。
血流アップで疲労物質が流れやすくなります。
2. 朝日で体内時計をリセット
年末年始に乱れた睡眠は、“朝の光”で戻すのが最速。
カーテンを開けて自然光を5分浴びるだけでOK。
年の瀬や正月明けに「なんかしんどい…」と感じるのは自然なこと。
でも、正しいケアをするだけで疲れはスッと抜けていきます。
今年は「無理に頑張る」ではなく、
“体にやさしい回復”を意識してみてくださいね。
それでは、また!
「骨盤は歪まない」って本当?正しい理解が矯正の第一歩
整体やエステなどでよく見かける「骨盤の歪みを整えます」というフレーズ。
でも実は、骨盤はそう簡単に歪むものではないことをご存じですか?
今日は「骨盤の歪み」について正しい知識をお伝えします。
●骨盤は頑丈な“骨の箱”
骨盤は、腸骨・坐骨・恥骨などいくつかの骨が強力な靭帯でつながってできています。
成人の骨盤は関節がほとんど動かないように安定しており、交通事故レベルの強い外力が加わらない限り、骨そのものが「歪む」ことはまずありません。
●「歪み」と呼ばれているものの正体
では、なぜ「骨盤が歪んでいる」と感じる人が多いのでしょうか?
実は、整骨院やエステでいう「骨盤の歪み」は、多くの場合骨そのものではなく筋肉や姿勢のバランスの崩れを指しています。
左右どちらかの筋肉が硬い・弱い
立ち方・座り方・歩き方にクセがある
妊娠・出産後で骨盤周囲の支持力が一時的に低下
こうした要因で骨盤周囲の筋肉の緊張や関節の位置関係が微妙に変わり、見た目として「骨盤が傾いている」ように見えることがあります。
●「骨盤矯正」ではなく「動きの矯正」が大事
骨盤そのものは歪みませんが、骨盤を支える筋肉のバランスや動作パターンは変えることができます。
お尻・太もも・体幹の筋肉をバランスよく使う
同じ姿勢を長く続けない
正しい立ち方・座り方を意識する
こうした習慣で骨盤まわりが安定し、見た目の左右差や違和感が改善していきます。
● 正しい知識で姿勢を作りましょう
「骨盤が歪んでいるから体調が悪い」と思い込む必要はありません。
本当に大切なのは、日常の動きや筋肉バランスを整えること。
正しい知識を持ち、ストレッチやトレーニングを取り入れて、骨盤まわりを元気に保つことが姿勢・快適な体への近道です。
夏に糖質を控えすぎると危険?熱中症リスクとの意外な関係
こんにちは、百です(*^^*)
夏になると「糖質は太るから控えよう」と考える方も多いですよね。
でも実は、糖質を極端に減らすと熱中症のリスクが上がることをご存じでしょうか?
今日はその理由を分かりやすく解説します。
1. 糖質は「体のエネルギー源」
人の体は、筋肉や脳を動かすときにまず**糖質(グルコース)**を使います。
特に夏場は暑さによって代謝が上がり、体温調節にもエネルギーが必要です。
糖質が不足すると、体がエネルギー不足になり、だるさ・めまい・集中力低下といった症状が出やすくなります。これは熱中症の初期症状とよく似ています。
2. 糖質がないと「水分保持力」が下がる
糖質は水分と一緒に体に貯えられる性質があります。
例えば、筋肉に蓄えられるグリコーゲンは 1gで約3gの水分を一緒に保持。
糖質が不足するとグリコーゲンが減り、水分保持力も下がるため、脱水しやすくなるのです。これも熱中症のリスクを高める大きな要因です。
ダイエットや健康を意識して糖質を控える方も多いですが、夏は特に「極端な糖質制限」は避けるのが安心です。
エネルギーをしっかり補給して、暑い季節を元気に乗り切りましょう!
カルシウムだけでは骨が強くならない理由~カルマグ比について~
こんにちは!百です(*^^*)
「骨を強くするにはカルシウム!」
昔からそう言われていますが、それは本当でしょうか?
確かにカルシウムは骨の主要成分ですが、マグネシウムの存在も忘れてはいけません。
実は、マグネシウムが不足すると、いくらカルシウムを摂っても骨がもろくなることがあるのです。
◆ マグネシウムの役割とは?
マグネシウムは300以上の酵素反応に関与する重要なミネラルで、以下のような働きがあります。
・カルシウムの代謝を助ける
・骨の石灰化を調整する
・神経と筋肉の興奮を抑える
・ビタミンDの活性化に関わる
中でも注目すべきは、カルシウムとのバランス。
このバランスが崩れると、骨は弱くなってしまいます。
◆ カルシウムを活用するために重要な「カルマグ比」
骨の健康において、
**カルシウム:マグネシウムの理想比率は「2:1」**
と言われています。
しかし現代人の食生活では、カルシウム過多・マグネシウム不足になりがち。
たとえば、乳製品や加工食品、サプリメントでカルシウムは摂れても、マグネシウムは不足している…というケースが多いのです。
この状態が続くと、
・骨密度が低下する
・筋肉がこわばる
・けいれんやこむら返りが起こる
・骨の修復が遅れる
といったトラブルにつながります。
◆マグネシウム不足になりやすい人の特徴
以下のような生活をしているとマグネシウムが不足しがちです。
1. インスタント食品や加工食品が多い人
→ こうした食品にはマグネシウムがほとんど含まれていません。
2. 甘いもの・アルコールが多い人
→ マグネシウムは糖の代謝やアルコールの分解にも使われるため、多く摂取すると消費が増えます。
3. ストレスが多い人
→ ストレスがかかると、尿からマグネシウムが排出されやすくなります。
4. 汗を多くかく人(スポーツ・夏の屋外活動など)
→ マグネシウムは汗からも排出されるため、夏場や運動習慣がある人も要注意です。
骨を強く保つには、カルシウムだけでなくマグネシウムとのバランスが大切。
知らず知らずのうちに不足していないか、ぜひ食生活を見直してみてください。
VIVA水道筋ではマグネシウムサプリメントの摂取もお勧めしています(*^^*)
**「骨密度=カルシウムだけではない」**
という視点を持つことで、より賢い健康づくりができますよ!
それでは、また(^^)/
フィットネス目線で選ぶ、夏におすすめの食べ物
暑くなると食欲が落ちたり、冷たいものばかり食べがち…。
でも夏こそ、体を動かすエネルギーをしっかりチャージすることが大切です!
筋肉を守り、代謝を落とさず、暑さに負けない体をつくる食材を紹介します✨
✅ 1. 鶏むね肉・ささみ
高たんぱく&低脂質の代表選手!
冷しゃぶサラダや、茹でて刻んで冷たい和え物にしても◎
夏は冷たくサッパリ食べやすい調理法がポイント。
✅ 2. 豆腐・納豆などの大豆製品
疲れやすい夏は胃腸に負担をかけにくい植物性たんぱく質がおすすめ。
冷奴、納豆ごはん、豆腐サラダでさっぱり補給!
✅ 3. 卵
良質なたんぱく質とビタミンB群を含む万能食材。
ゆで卵にしておけば、冷蔵庫にストックしてパパっと食べられます。
✅ 4. きゅうり・トマト・オクラ
夏野菜は水分・ミネラルがたっぷり。
カリウムも多く、汗で失われがちなミネラルバランスを整えます。
サラダや浅漬けで冷たく食べても、味噌汁に入れて温かくとってもOK!
✅ 5. スイカ・メロン
「果物は糖質が多いからNG?」
そんなことはありません!
水分・カリウム補給にピッタリなので、トレーニング後の水分補給代わりに少量食べるのはおすすめです。
✅ 6. 梅干し
汗で失われがちな塩分補給に!
クエン酸も含まれていて、夏バテ防止&疲労回復に◎
冷やし茶漬けに入れたり、きゅうりと和えるのもさっぱりしておすすめ。
【ポイント】
夏は冷たいものばかりに偏ると、胃腸が弱り、栄養吸収力が落ちます。
サラダだけでなく、温かい味噌汁・スープ・温野菜を少しでも組み合わせて、内臓を冷やしすぎないのが体づくりのコツです!
◎ まとめ
✅ 夏もたんぱく質をしっかり!
✅ 夏野菜や果物で水分&ミネラルを!
✅ 内臓を冷やしすぎず、疲労回復を意識!
美味しく食べて、夏のトレーニングをもっと効率よく!
食事でパフォーマンスを上げていきましょう🔥
ボディメイクは“姿勢づくり”から始めよう
「お腹をへこませたい」
「ヒップアップしたい」
「くびれが欲しい」
そんなボディメイクの目標を持って頑張っている方、多いですよね。
でもちょっと待ってください。
理想の体をつくるには、筋トレや食事管理だけでは足りないことがあるんです。
それが“姿勢”。
◆ 姿勢が崩れるとボディラインも崩れる?
例えばこんな姿勢、思い当たりませんか?
✅ 猫背で肩が前に丸まっている
✅ 腰が反りすぎてお腹がぽっこり
✅ 骨盤が前に突き出ている
このような姿勢は、筋肉のバランスが崩れてしまい、
お腹・お尻・太ももなどのラインに影響を与えます。
例えば猫背だと、お腹の筋肉が緩みやすく、下腹が出やすくなります。
反り腰だと、お尻が後ろに突き出る一方で、太もも前が張りやすくなったりします。
つまり、**姿勢は“ボディラインの土台”**なのです。
◆ 正しい姿勢がボディメイクの近道
姿勢を整えると、
✔️ 骨盤の位置が安定して、お腹が引き締まりやすい
✔️ お尻の筋肉が正しく使えてヒップアップ
✔️ 代謝が上がりやすい
など、トレーニングの効果が出やすくなります。
逆に、姿勢が悪いままでは、せっかくの筋トレも
「効かせたい場所に効かない」
「変なところが張る」
など、もったいない結果に…。
◆ 姿勢改善はストレッチ+運動が大事
姿勢を整えるには、硬くなっている筋肉をストレッチでゆるめつつ、
弱くなっている筋肉を正しく使えるように動かすトレーニングが大切です。
ポイントは、姿勢は脳がコントロールしているということ。
自分で動いて、脳に「正しい姿勢はこれだよ」と覚えさせることが、姿勢とボディラインを変えるコツです。
◆ 姿勢から、理想のカラダへ
理想の体を手に入れたいなら、
**「まずは姿勢を整える」**ことから始めてみてください。
姿勢が変わると、見た目も動きも変わり、
トレーニングの効果もグッと高まります。
美しい姿勢で、理想のカラダを手に入れましょう!
一人でやるのが不安な方は、ぜひ私たちに相談してくださいね😊
~夏を元気に乗り切る~ 知っておきたい熱中症予防の基本
こんにちは!百です(*^^*)
「今年の夏も暑くなりそう…」
「気づいたら頭がボーッとしてる」
そんなとき、注意したいのが熱中症です。
特に屋外はもちろん、室内でも熱中症になるリスクは高まっています。
今回は、誰でもできる“熱中症対策の基本”をわかりやすくお伝えします!
◆ そもそも熱中症ってなに?
熱中症とは、体内の水分や塩分のバランスが崩れて、体温調整がうまくできなくなる状態のこと。
症状としては、
✅ 頭痛・吐き気
✅ めまい・立ちくらみ
✅ 筋肉のけいれん(足がつるなど)
✅ 意識がぼんやりする
などがあり、重症化すると命に関わることもあります。
◆ こんな人は特に注意!
✔️ 高齢者・子ども
✔️ 屋外での運動が多い人
✔️ 体調がすぐれない日
✔️ マスクを長時間つけている人
これらの条件が重なると、熱が体にこもりやすく、気づかないうちに熱中症になるリスクが高くなります。
◆ 予防のために今すぐできること
① こまめな水分補給を
「のどが渇いた」と感じたときにはすでに軽い脱水状態です。
のどが渇く前に、こまめに水分をとることが大切!
特に汗をたくさんかいたときは、水だけでなく、塩分やミネラルも補給できるドリンクを選びましょう。
② 涼しい服装・場所を選ぶ
吸汗速乾性のある服や、風通しの良い素材を選ぶことで体温調節がしやすくなります。
最近は男性でも日傘を利用されている方が増えましたね(*^^*)
日陰やエアコンのある場所を活用して、**「がまんしないこと」**が大事です。
③ 睡眠・食事をしっかりと
寝不足や栄養不足は、熱中症にかかりやすい体になります。
特に朝食を抜くと、体温調整に必要な水分や塩分が不足してしまうので注意!
④ 運動時の注意点
運動中は普段より汗を多くかくため、開始前・途中・終了後に水分をとる習慣を。
屋内でも、風通しをよくして、体温を上げすぎないようにしましょう。
熱中症は、ちょっとした油断が命に関わる危険につながることもあります。
でも、日々の対策でしっかり予防することができます!
「まだ大丈夫」は禁物。
水分・塩分・休息、この3つを意識して、暑い夏も元気に乗り切りましょう!
お勧めサプリ「クレアチン」について
「クレアチンって筋トレしてる人が飲むやつでしょ?」
そんなイメージを持っていませんか?
実はクレアチンは、アスリートだけでなく、健康的に体を変えたい人・疲れやすさを感じている人にもおすすめの成分なんです!
今回は、そんな「クレアチン」の効果をわかりやすく解説していきます。
◆ そもそもクレアチンってなに?
クレアチンは、体内に元々あるアミノ酸の一種で、主に筋肉や脳に存在しています。
肉や魚などからも摂取できますが、運動でしっかり効果を出すには、サプリで補うのが効率的です。
※肉や魚から十分に取るには1㎏程必要になり、ハードルが高く、カロリーオーバーになる
◆ クレアチンの主な効果
✅ 筋力アップ・パワー向上
クレアチンは、瞬発的なエネルギー(ATP)をすばやく再合成する力を持っており、筋トレや短距離走など、爆発的なパワーが必要な場面で力を発揮します。
「いつもよりもう1回多く上がった!」
「重さに余裕が出てきた!」
そんな実感が得られやすくなります。
✅ 筋肉量の増加サポート
クレアチンを摂取すると筋肉内に水分が増え、筋肉の張りや大きさが出やすくなります。
さらに、トレーニングで追い込める回数が増えるため、筋肥大の効果が高まりやすいのです。
✅ 疲労軽減・回復のサポート
クレアチンは、エネルギー回復を早めてくれるため、トレーニングの合間の回復力もアップ。
疲労感が少なくなることで、継続的な運動の助けにもなります。
✅ 脳への良い影響も?
近年の研究では、脳の疲労軽減・集中力の維持にも関わっているという報告もあります。
勉強や仕事でのパフォーマンスサポートにも注目されつつあります。
✅ 筋トレやスポーツをしている人
✅ 筋力をつけて代謝を上げたい人
✅ 疲れにくい体を作りたい人
✅ トレーニングの質を高めたい人
「運動の効果をもう一段階アップさせたい!」
そんな方には、ぜひ一度試してほしいサプリです。
◆ 飲み方のポイント
・1日3〜5gが目安(体格により変動)
正しく取り入れれば、トレーニングの質や体の変化に大きく影響してくれます。
「もっと効率よく鍛えたい」「疲れやすさをなんとかしたい」そんな方は、ぜひ活用してみてくださいね!
~腰痛・ポッコリお腹の原因~反り腰とは
「立っていると腰が痛い…」
「お尻が後ろに突き出て、お腹もぽっこり…」
それは**“反り腰”**が原因かもしれません!
反り腰は見た目の問題だけでなく、腰痛・肩こり・膝の痛みなど、さまざまな不調のもとになることもあります。
今回はそんな反り腰について、わかりやすく解説していきます(^^)/
◆ 反り腰ってどんな状態?
本来、腰の部分には少しだけ自然なカーブ(前弯)があります。
でもこのカーブが必要以上にきつくなってしまった状態が「反り腰」です。
反り腰になると…
✅ 腰の骨が前にグッと反る
✅ 骨盤が前に傾く(前傾)
✅ お腹が前に出て、お尻が後ろに突き出る
✅ 腰やもも前の筋肉がガチガチに…
という状態になりやすく、見た目にも疲れやすくなります。
◆ 反り腰の主な原因
ではなぜ反り腰になってしまうのでしょう?
実は、日常の姿勢や筋肉バランスの崩れが大きく関係しています。
✅ 長時間のデスクワーク
✅ ヒールの高い靴をよく履く
✅ 腹筋やお尻の筋力が弱い
✅ 太ももの前や腰の筋肉が硬い
✅ 妊娠・出産後の骨盤の傾き
…など、生活習慣の中に原因が隠れていることが多いです。
◆ ストレッチだけじゃなく“動き”が大事!
反り腰を改善しようとして、腰や太もも前をストレッチする人も多いですよね。もちろん大切なことですが、それだけでは不十分なんです。
反り腰の根本的な原因は「骨盤を支える筋力の弱さ」や「脳が正しい姿勢を認識していないこと」。
つまり、自分で動いて“正しい姿勢”を脳と体に覚えさせることが必要です。
◆ 改善のためのポイント
✔️ お腹(特に下腹)とお尻の筋肉を意識して使う
✔️ 骨盤をまっすぐ立てる感覚を覚える
✔️ 股関節・太もも前の柔軟性をアップ
✔️ 日常の姿勢を意識する(座る・立つ・歩く)
✔️ トレーナーのサポートで、正しい動きを習得する
◎ まとめ
反り腰は「クセだから仕方ない」とあきらめる必要はありません!
正しい動きと筋力バランスを整えていけば、自然と美しい姿勢に近づいていきます。
「私って反り腰かも?」
「腰がいつも疲れる…」
そんな方は、ぜひ一度ご相談くださいね。あなたに合った改善法をご提案します(*^^*)